|
私が手がけるプロジェクトに「GASSHO projects」というものがある。 各分野の技を組み合わせる、互いに手を取り合う、という作品製作におけるプロセスと日本建築の合掌造りを連想させたネーミングだ。 日本のものづくり産業は周知の通り分業制から成り立つ。大概の製造業では「設計、下地、成形、加飾(製造)>仲買、問屋(流通)>小売(販売)>購買層」という流れが存在し、そこにはヒエラルキーとしての階層構造が存在する。 フラットな立場を求めるのは誰しもだが、その意味合いが各階層にとって異なる事がジレンマになる。仮にケン・ウィルバー「スペクトラル理論」に当てはめると、定義された成果を目指して邁進する層(オレンジ)もいれば、多様性を認められて各理念に基づいて行動したい層(グリーン)もいる。 そこで我々GASSHO projectsは手仕事業界だからこそ成り立つ「ティール」としての組織構成を基にした。合資や共同開発という言い方も近からず遠からずではあるが、そもそもの目標が「よりおもしろいものを既に各個人が所有している資産(技やセンス)で生み出していく」事であり、同時にスタート地点でもある事が大きな違いとなる。 そして市場への流通を各ステップを維持したまま既存の業界から同ステップにいる異業界の流通経路へと置換していくことで我々の見せ方をまるっと委託し、その多様性を狙う。目利きとしての問屋的立ち位置は必要だし、小売店としての発信力も魅力的だが、ジェンダーや国境の壁がなくなりつつある昨今で業界の壁を飛び越える術が無いわけがない。そういう意味では工芸や手仕事を一切学んだことのない美術家と産地工場で製造に携わる職人が直接共に同じ轆轤(ろくろ)であーだこーだ言いながら合作を手がける事は不思議ではない。 確かにリーダーとしての役割は不可欠ではあるけど、目標の共有と各ロールの相互認識によってヒエラルキーというよりは寧ろ純粋に他領域リテラシーを各社が取り入れ、結果(目に見えるカタチ)としてスピーディーに具現化される。各領域が本当の意味でフラットになる連合組織なのだ。 モジュール的な流通経路とインテグラルな生産体制がどちらもがインプロバイズにより構成されるので、生産側である我々が予想以上の形を生み出し携わる事ができる。 創り手、作り手、通訳者、発信者がこんな流れでお届けする作品たちをお楽しみいただければ幸いです。
0 Comments
What is the difference between who can and cannot access to others?
The lower the point at which a person feels lonely, the more seeking access to others. If you are loved and do not feel a barrier to access to the outside, the point becomes low. And people who do not belong to the majority, they try to convey access to the outside through an indirect medium. After all, people want to connect with someone. The person who feels loneliness, who is the person on the sending side, first seeks access from those who can tell the majority. Those who are difficult to feel the loneliness who carry such a messenger can convey the creator's view of the world in an interesting way. I need to be alone after all. However, it's unlike emptiness and despair, I simply don't miss the opportunity to focus on the isolated spirit world. In the modern society where parents, friends and family can check my behavior at any time in the Internet society, the only way to make anonymity is to create another person in myself. Creating art is the only way for me to make it real. So it always doesn't have to be shown 'Who made this'. |
Categories
All
Archives
November 2023
Author |
Powered by
 Create your own unique website with customizable templates.
Create your own unique website with customizable templates.
 Create your own unique website with customizable templates.
Create your own unique website with customizable templates.
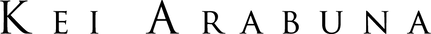



 RSS Feed
RSS Feed